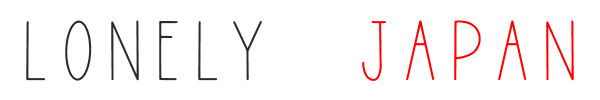高い、大きな、暗い土手が、何処から何処へ行くのか解らない、静かに、冷たく、夜の中を走っている。その土手の下に、小屋掛けの一ぜんめし屋が一軒あった。カンテラの光りが土手の黒い腹にうるんだ様な暈を浮かしている。私は、一ぜんめし屋の白ら白らした腰掛に、腰を掛けていた。何も食ってはいなかった。ただ何となく、人のなつかしさが身に沁むような心持でいた。卓子の上にはなんにも乗っていない。淋しい板の光りが私の顔を冷たくする。
私の隣りの腰掛に、四五人一連れの客が、何か食っていた。沈んだような声で、面白そうに話しあって、時時静かに笑った。その中の一人がこんな事を云った。
「提灯をともして、お迎えをたてると云う程でもなし、なし」
私はそれを空耳で聞いた。何の事だか解らないのだけれども、何故だか気にかかって、聞き流してしまえないから考えていた。するとその内に、私はふと腹がたって来た。私のことを云ったのらしい。振り向いてその男の方を見ようとしたけれども、どれが云ったのだかほんやりしていて解らない。その時に、外の声がまたこう云った。大きな、響きのない声であった。
「まあ仕方がない。あんなになるのも、こちらの所為だ」
その声を聞いてから、また暫らくぼんやりしていた。すると私は、俄にほろりとして来て、涙が流れた。何という事もなく、ただ、今の自分が悲しくて堪らない。けれども私はつい思い出せそうな気がしながら、その悲しみの源を忘れている。
それから暫らくして、私は酢のかかった人参葉を食い、どろどろした自然生の汁を飲んだ。隣の一連れもまた外の事を何だかいろいろ話し合っている。そうして時時静かに笑う。さっき大きな声をした人は五十余りの年寄りである。その人丈が私の目に、影絵の様に映っていて、頻りに手真似などをして、連れの人に話しかけているのが見える。けれども、そこに見えていながら、その様子が私には、はっきりしない。話している事もよく解らない。さっき何か云った時の様には聞こえない。
時時上手の上を通るものがある。時をさした様に来て、じきに行ってしまう。その時は、非常に淋しい影を射して身動きも出来ない。みんな黙ってしまって、隣りの連れは抱き合う様に、身を寄せている。私は、一人だから、手を組み合わせ、足を竦めて、じっとしている。通ってしまうと、隣りにまた、ぽつりぽつりと話し出す。けれども、矢張り、私には、様子も言葉もはっきりしない。しかし、しっとりした、しめやかな団欒を私は羨ましく思う。私の前に、障子が裏を向けて、閉ててある。その障子の紙を、羽根の撚れた様になって飛べないらしい蜂、一匹、かさかさ、かさかさと上って行く。その蜂だけが、私には、外の物よりも非常にはっきりと見えた。
隣りの一連れも、蜂を見たらしい。さっきの人が、蜂がいると云った。その声も、私には、
はっきり聞こえた。それから、こんな事を云った。
「それは、それは、大きな蜂だった。熊ん蜂というのだろう。この親指ぐらいもあった」
そう云って、その人が親指をたてた。その親指が、また、はっきりと私に見えた。何だか見覚えのある様ななっかしさが、心の底から湧き出して、じっと見ている内に涙がにじんだ。
「ビードロの筒に入れて紙で目ばりをすると、蜂が筒の中を、上ったり下りたりして唸る度に、目張りの紙が、オルガンの様に鳴った」
その声が次第に、はっきりして来るにつれて、私は何とも知れずなつかしさに堪えなくなった。私は何物かにもたれ掛かる様な心で、その声を聞いていた。すると、その人が、またこう云った。
「それから己の机にのせて眺めながら考えてると、子供が来て、くれくれとせがんだ。強情なでね、云出したら聞かない。己はつい腹を立てた。ビードロの筒を持って縁側へ出たら庭石に日が照らっていた。」
私は、日のあたっている舟の形をした庭石を、まざまざと見る様な気がした。
「石で微塵に毀れて、蜂が、その中から、浮がるように出て来た。ああ、その蜂は逃げてまったよ。大きな蜂だった。ほんとに大きな蜂だった」
「お父様」と私は泣きながら呼んだ。けれども私の声は向うへ通じなかったらしい。みんなが静かに立ち上がって、外へ出て行った。
「そうだ、矢っ張りそうだ」と思って、私はその後を追おうとした。けれどもその一連れは、もうそのあたりに居なかった。そこいらを、うろうろ探している内に、その連れの立つ時、「また行こうか」と云った父らしい人の声が、私の耳に浮いて出た。私は、その声を、もうさっきに聞いていたのである。月も星も見えない。空明りさえない暗闇の中に、土手の上だけ、ばうと薄白い明りが流れている。
さっきの一連れが、何時の間にか土手に上がって。その白んだ中を、ぼんやりした尾を引く様に行くのが見えた。私は、その中の父を、今一目見ようとしたけれども、もう四五人の姿がうるんた様に溶け合っていて、どれが父だか、解らなかった。
私は涙のこぼれ落ちる目を伏せた。黒い土手の腹に、私の姿がカンテラの光りの影になって大きく映っている。私はその影を眺めながら、長い間泣いていた。それから上手を後にして、暗い畑の道へ帰って来た。
by rantouda